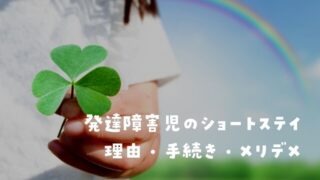重度知的障害を伴う自閉スペクトラム症な我が家の末っ子は現在5歳8か月。
癇癪やパニックを起こすと、物を投げたり人を傷つけてしまうことがあり、その対処法にとても困っていました。
SNSで動画でアップしたところ、特別支援学校の先生をしている方から個別にメッセージをいただいたんです!
先生が学校で実際に行っている対処法や考え方を聞かせていただき、それがとても参考になったので「同じように悩んでいる方へぜひシェアをさせてください!」とお願いしたところ、快くご承諾いただきました~(≧▽≦)
個人情報がわからないようにするためと、ブログ用にわかりやすくするために、意味は変えないように気を付けながら一部編集を加えてお伝えします。
発達障害児の癇癪やパニックはどんな感じ?
まず、わが子が癇癪やパニックを起こして暴れるときの様子をご紹介します。
ひどい時はとても撮影なんてできないのですが、たまたま娘が撮ってくれた動画があるのでだいたいの様子は伝わるかなと思います。
これは5歳0か月のときの様子です。
そしてメッセージをいただくきっかけになったのがこちらの投稿です。
↓
この投稿をInstagramで見る
撮影前に、トイレのドアをガンガンと壁にぶつけて壁の穴がまた大きくなりましたが、全体的に見ると暴れる時間は短くなっていて、これでも以前よりは少しマシになっています。
このように、うちの末っ子は自分ではなく他人に対して
- 髪の毛を引っ張る(ゴッソリ抜けるくらいの力で)
- 叩く
- 蹴る
- つねる
- 引っかく
- 噛みつく
という行動をとります。
原因は観察している限りでは大きく2つ。
- 自分の思いが伝わらないときや思い通りにいかないとき
- 突然のパニック(病院の先生によると嫌なことを思い出すなどのフラッシュバックが考えられるとのこと)
私の中では①を「癇癪(かんしゃく)」、②を「パニック」と区別しています。
癇癪のときはだいたい原因がわかりますが、パニックのときは突然何の前触れもなく暴れ出すことが多いので、私が見ていないところで娘に手を出してしまうときなどは本当に困ります。
発達障害の子どもが癇癪やパニックで攻撃的になっているときの対処法は?

そこで、先生が学校でやっている具体的な対処法を教えていただきました!
共感する
- やだったね
- 疲れたね
- やりたくないよね
- 暑いよね
- イライラするね
など、本当の感情は分からないにしても「そうかな?」と考えられる気持ちを言語化して繰り返し伝えてることが大事だとのこと。
危害が広がらないようにする
子どもの気持ちに共感しながらも、他害や物に当たらないように気を付けなければなりません。
- 背後からぎゅっと抱きしめて手を握る
- 前から腹筋を手伝うように子供の足を大人のお尻の下にし膝を少し固定し、ほかに危害がないようにする
その他の効果的な対処法
- 噛む場合は「噛むならこれにして!」というグッズを用意する
- 指先をぎゅっと掴むように結構力強く圧をかける
- 頭のマッサージや肩、二の腕、太もも等も強めにギュギュと圧をかける
癇癪を起している気持ちに寄り添う

先生と何度かやり取りをさせていただき、とても素晴らしいな~と思った考え方をご紹介します!
「こういう子が大人になっても、就労しても愛される!」
私は「お母さんたちにやってみてください。」はあまりお伝えしてないなと思いまして…「まず学校でやらせてください。」とお伝えしていました。学校でできるようになるとご家庭でも癇癪が減ってきたという報告を受けることが多いです。「家ではこれ以上頑張らない。第三者が頑張る。」という考えでやっています。
「癇癪に寄り添うのではなく、癇癪を起こしている気持ちに寄り添う」と良いのかなというのは常々思っています
癇癪をなくすという考えは難しいです。大人でもイライラすることむしゃくしゃすることがあるのと同じように、自閉の子だって大人になってもイライラはします。小さいうちにそのイライラのぶつけ方を見つけたり、癇癪を起している時間が少しずつ(10秒でも)短くなるように時間をかけてフォローしてあげていくとよいのかなと思っています。
やってみたけどダメだった~ということももちろんありますので、色んなことを試していけると良いのかなと思います。凸凹ちゃんの人生、まだまだこれからですね!
とても愛にあふれるメッセージをたくさんいただき、勉強になりましたし、勇気と元気がわいてきましたー!
本当にありがとうございました☆
まとめ
癇癪やパニックを起こしたとき、特別支援学校の先生が実際にやっている対処法や考え方をご紹介しました。
「否定をせずにまずは共感しながら、いけないことはいけないと伝える」というのがとても納得できたし、これならうちでもできそうだと思いました。
その子の特性やそのときの状況によって、暴れ方も違ったりするし、いつもできている対処法ができないこともあります。
そう簡単に解決できる問題ではなくて時間と根気のいることだけど、きっと伝わると信じて向き合っていきたいと思います。