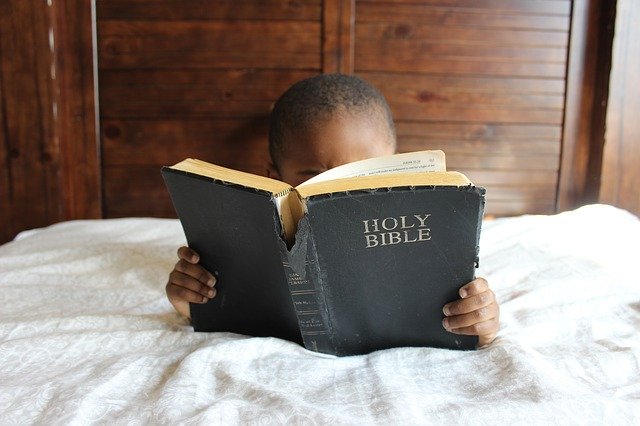発達障害グレーゾーン+HSCの特性を薄く広く持っていると思われる小4の長男が、学校で疲れる理由をやっと話してくれました。

そのことについて担任の先生に相談したところ、すぐに動いてくださいました。
担任の先生と保健室の先生がまず本人への聞き取りをしてくれ、発達支援コーディネーターの先生と私との面談をセッティングしてもらえたのです。
小学校では発達障害グレーゾーンの子どもにどのような支援を行ってもらえるのか、家庭でできることやその他機関への相談など、話した内容やいただいたアドバイスをまとめています。
同じように発達障害グレーゾーンの小学生の子育てで悩む方へ、参考になれば幸いです。
発達支援コーディネーターと母親との面談

発達支援コーディネーター(以下「K先生」)とは初めての顔合わせでした。
K先生は、私が担任の先生に長男の訴えをまとめた紙をコピーしたものを持っていて、だいたいの内容はわかっていました。
学級の中で問題があったり困りごとがある生徒がいると、担任からK先生へまず相談をして、その後支援が必要かどうかということを検討していくそうです。
うちの長男については今まで担任からの相談などは全くなかったので、今回の件で初めて長男のことを知ったとのこと。
すでに身体症状が現れていて、家で爆発(家族に当たり散らす)していることから「学校で相当な我慢をしていると思いますよ」と言われました。
K先生にはこれまでの経緯をまずお話しました。
- 2年生の頃から学校と家での違いが大きかった
- まずは地元の小児科に相談
- その後、本土の病院を受診して検査を受けた
- 検査結果では自閉スペクトラム症の傾向はあるものの診断はつかず
- 地元の発達外来で末っ子の担当医に引き継いでもらったけど、継続的な診察は不要とのこと
- 父親と離れて少し落ち着いたけど、最近になってまた疲れが見えるようになってきた
- 長男が学校で疲れる理由を話してくれた
K先生の話では
- 長男は自分のペースや「こうあるべき」ということを乱されるのがとても辛いタイプ
- 担任の聞き取りからクラスに苦手な子がいる(意地悪をされるとかじゃなく、授業中に勝手に動き回ったり大声を出したりする多動気味な子⇒席を離すなどで対処)
- 長男自身は生真面目だから苦手な子に反抗することもなく、苦手なことから逃げ出すこともなく、学校ではルールに従って一生懸命生活するため、一日が終わるころにはもう我慢が限界に達していっぱいいっぱい。それが家で爆発する。
- 長男は考え方や受け止め方、表現が極端になってしまうタイプ
- 家では家族、特に妹にペースを乱される
- 妹も口が悪い(キツイことをサラッと言ってしまう)のは知ってる⇒ここも今後友達とのトラブルになりかねないから指導が必要
ということでした。
さすが発達支援に詳しい先生だから、私がうまく説明できないことも理解してるし、的確に表現してくれて「そうそう、そうなんです!」っていう感じで、かなりスッキリしました。
家での対処法

まず、家でできる対処法についてアドバイスをもらいました。
- 長男と妹、二人にお互いの不満を聞き取り
- 家庭のルールを決めて紙に書き出して貼っておく
- ルールが守られたときに大いに褒める(カレンダーにシールを貼る、ご褒美をあげるなど目に見える形で)
- 日課表を作って貼っておく
長男のようなタイプは、言葉で話すよりも目で見てわかりやすい方法をとるのが良いと教えてもらいました。
確かに、ちょっと前までも「日課表があった方が生活しやすい」ということで壁に貼っていたんですよね。
でも、何かのきっかけに(日課表通りにできなかった)自分で取ってしまったんです。
その話をすると
[say name=”K先生” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/170963.jpg”]細かく決めてしまうと守れないことがあるから、大まかに決めるといいですよ[/say]
とのことでした。
なるほど!できることから早速やっていこう!
長男が担任の先生と保健室の先生に話したこと

発達支援コーディネーターとの面談が終わってから、保健室の先生とも話をしました。
保健室の先生は長男が2年生の時から何かと相談して、長男にも私にも親身になって関わってくださって、大変お世話になっている先生です。
先週の木曜日(11/14)担任の先生と、保健室の先生がそれぞれ長男の学校での困りごとについて話を聞いてくださったそうです。
- 座りっぱなしで動けない授業のときは体がムズムズする
- 卒業式の練習や本番のときがいちばん辛かった
- 体育の時や理科の実験など動けるときは大丈夫
- 金曜日が最悪
- 中休みや昼休みはムズムズを発散させるために運動場で走っている
- 家では妹に特に不満がある
家で私に話してくれたこととだいたい同じ内容でしたが、驚いたのは「休み時間に走ってる」ということ。
これは先生もいい意味で驚いていて、
[say name=”保健室の先生” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/128711.jpg”]2年生から見てきたけど、ずいぶん成長したな~って思ったんです。自分で対処法を考えて、何とか解決しようとしているんですね![/say]
運動は苦手で、休み時間には図書室に行って本を読むのが好きな長男。
そういえば、12月の持久走大会に向けて休みの日も「公園に行って走る」って最近言い出したんですよね。
少しずつ成長してるんですね。
家出の話もしました。

すると
[say name=”保健室の先生” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/128711.jpg”]お母さんの対応は良かったと思いますよ。否定せずに淡々と事実を説明する。[/say]
[say name=”母” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/wink.jpg” from=”right”]そうですか?良かった~^^[/say]
[say name=”保健室の先生” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/128711.jpg”]それに、放課後学童へ行かずにお母さんとの時間、一人でゆっくり過ごす時間ができることは、Yくんにとってすごく安らげる時間になると思いますよ。[/say]
[say name=”母” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/wink.jpg” from=”right”]そうなんですね!良かった~^^[/say]
保健室の先生にそう言ってもらえて、少し安心しました。
学校でのムズムズ対策

学校で授業中にムズムズして我慢できなくなった時にどうしたらいいのか?
その時の対処法についても先生と長男の間でルールを決めてくれたそうです。
[say name=”保健室の先生” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/128711.jpg”]合言葉は「お腹が痛いです。」そしたら先生は「保健室に行っておいで」って言ってくれるから。担任の先生じゃなくてもわかるようにしておくから大丈夫だよ^^[/say]
[say name=”長男” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/bikkuri-otoko.jpg”]でも書写の時間とかは担任の先生じゃない・・・[/say]
[say name=”保健室の先生” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/128711.jpg”]担任の先生じゃなくてもわかるようにしておくから大丈夫!合言葉は「お腹が痛いです」だよ^^[/say]
その約束をした翌日、長男が最悪だと思っている金曜日でした。
特に書写の時間は習字道具を使うから絶対に動けないらしく、苦痛でたまらない時間だそうです。
[say name=”保健室の先生” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/128711.jpg”]でもね、その日は保健室に来なかったんですよ![/say]
[say name=”母” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/wink.jpg” from=”right”]そうなんですね~![/say]
[say name=”保健室の先生” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/128711.jpg”]あの日は5、6時間目が総合で活動の時間だったから、「ここまで頑張れば!」っていうのが本人の中であったのかも。[/say]
[say name=”母” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/wink.jpg” from=”right”]そういえば、いつもは金曜日の放課後は大荒れなのに、あの日は作った作品を嬉しそうに持って帰ってきて見せてくれました^^[/say]
一日のスケジュールを見て、自分の中でうまく処理しようとしているのかもしれません。
今後の進め方

今後の進め方についてK先生から提案してもらったことは
- 水曜日にスクールカウンセラーの先生が来ているので、本人が希望すれば話す時間を作ってみる。
- 早くて12月半ばから通級指導教室のお試しができるので、本人が希望すればやってみる。
- 地元の病院の発達外来を早めに受診する。
- 家でできる対処法をやっていく。
スクールカウンセラーと通級指導教室のお試しについては、本人に聞いてみたら「行く」と即答だったので、すぐにお願いしました。
地元の発達外来は、以前一度診てもらったことがあるんですが、本土から月に一回しか先生が来ないので、来月の予約が取れるかどうか・・・というところです。
※12月の予約はやっぱり取れなかったので1月に入れてもらいました。2か月後か・・・( ;∀;)
まとめ
今回、初めてK先生と話をすることができて本当に良かったと思いました。
[say name=”K先生” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/170963.jpg”]話を聞いたところでは自閉スペクトラム症寄りだと感じました。身体症状が出ているので、診断の有無に関わらず支援が必要だと思います。[/say]
とのこと。
先生も「急いだほうがいい」と判断したそうで、急遽直近の空き時間を利用して面談をセッティングしてもらえて助かりました。
[say name=”K先生” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/170963.jpg”]本当は小児精神科でセラピーなんかを受けるといいのかもしれないけど…島じゃ紹介できる所が1か所しかなくて…本土だったらたくさん紹介できるのにってもどかしい気持ちもあります。でも、島は島なりのゆったりした環境で競争も少ないし、子どもにとっては良い面もあるんですよね。[/say]
うーん。これはわかります。
確かに本土の方が選択肢は多い。
いずれは実家のある本土に戻るとは思うんだけど、せっかく今の環境に慣れて、ピアノや合唱など楽しめる習い事もある。
まずはここでできることをやってみて、それでも他の方法が必要だったら、本土に定期的に通うとか、本格的に引っ越すとか次の方法を考えればいいかなと思っています。
とにかく「本人が限界まで我慢せずうまくガス抜きをする方法を習得できるようにサポートしていく」ということを、学校でも家庭でも共通して意識していくのが大事です。
昨日は学童に行かず直接家に帰ってきた長男は、夜まで穏やかに過ごせました。
妹はいじけてたけど、夜は一緒に仲良く遊んでたんですよねー。
このまま学童辞めるって言うかな・・・と思ってたんですが、なんとクラスでわりと仲の良い子が同じ学童に入ってきたそうで
[say name=”長男” img=”https://ddkids-online.com/wp-content/uploads/2019/11/bikkuri-otoko.jpg”]来週から学童に行く!冬休みも行く![/say]
と言っております^^
これからどうなるかわからないけど、行きたいときは行けばいいし、行きたくないときは無理して行かなくてもいいし、と思ってます。
とにかく、母はいつでも動ける態勢を作っておく。
そして子どもの前では演技派女優であること。
これ超大事だと2人の先生もおっしゃってました(^_-)-☆